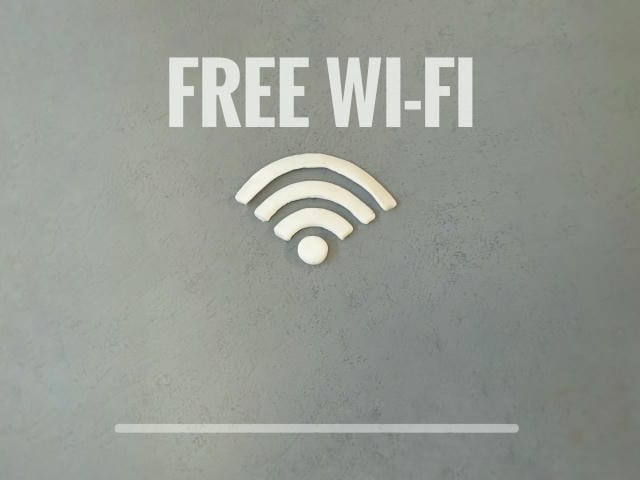コンピューターやタブレット、スマートフォンといった情報端末は、業務効率の向上や情報活用の新たな可能性をもたらしている。その一方、企業や組織に存在するこれらの端末がサイバー攻撃の標的となるリスクが急速に増大している。こうした背景から、情報システムの守りの最前線を担う対策としてエンドポイントセキュリティの重要性が明らかになっている。従来、情報システムのセキュリティ対策といえば、ファイアウォールやネットワーク監視を中心とした外部との境界線に主軸が置かれていた。しかし、クラウドサービスやテレワークの普及、多様なモバイル端末の業務利用拡大によって、これまで一元管理が可能だったネットワークの境界があいまいとなり、防御の構築がより複雑になっている。
そのため、個々の端末ごとに適切な防御機能を持たせるエンドポイントセキュリティが必須となっているのである。エンドポイントセキュリティの主な役割は、端末を介した不正な操作やサイバー攻撃の侵入・拡散を防ぎ、機密データやシステム全体を守ることにある。具体的として、不正なプログラム侵入の検出と隔離、マルウェアやランサムウェア感染の防止、脆弱性を悪用する攻撃への対応、権限のないアプリケーションの実行制限などが挙げられる。さらに、端末の利用ログの収集・監査や、ソフトウェア・パッチの適切な配布・管理、リモートからのデータ消去や端末制御も重要な機能だ。多様化するサイバー攻撃は、標的となる端末のOSやアプリケーションの脆弱性を狙うものが増えている。
なかでも、標的型メールを使った攻撃や、不正なWebサイト経由でのマルウェア感染は日常的に発生している。また、従業員自らが意図せず不正ファイルを開くことによる社内ネットワーク全体への拡散も深刻な問題である。こうしたリスクに対抗するにはパターンファイルによるマルウェア検知に加え、ふるまい検知やサンドボックス、未知の脅威にも対応する技術の組み合わせが有効とされている。エンドポイントでの不正行為は内部不正も侮れない脅威である。例えばUSBメモリや記録媒体を用いた情報の持ち出し、権限を持たない操作、不審な通信など、端末単位でのきめ細かな監視と制御は欠かせない要素である。
許可されたアプリケーションだけが動作する仕組みや、管理者の確認なく外部ストレージを使えない設定などは、この対策に大いに役立つ。実際にエンドポイントセキュリティを導入する際は、単なるウイルス検知ソフトの導入だけでなく、組織全体の運用ルールに沿った構成とすることが求められる。セキュリティポリシーと整合性を取りつつ、多数の端末に対して容易に管理・監視できるよう、中央管理型の仕組みを持つ製品の採用が推奨されている。また、OSやソフトウェアのアップデート運用、自動での修復や隔離処置、利用者の行動分析やリスク検知も併せて重要な観点である。昨今注目されているのは、多層防御という考え方である。
エンドポイントセキュリティの仕組みを、クラウド上の管理サービスや他のセキュリティ対策と連携させ、攻撃全体の流れを横断的に捉えて検知と防御を強化するものである。端末側で異常の兆候が発見されれば、ネットワーク全体へ即時連携し封じ込め対策を実施するなど、リアルタイム対応への進化が求められている。業務の現場では、従業員の利便性も重要視されるため、過度な制限による業務妨害と防御レベルの最適バランスも重要となる。システム管理者による監視と端末利用者自身のセキュリティ意識向上を合わせて高めることが、サイバー攻撃と不正リスクを低減させるうえで不可欠である。今後、攻撃者の手口はより巧妙化し、自動化すら進むと予測されているため、エンドポイントセキュリティの技術も不断に進化が求められる。
組織においても、導入後の形骸化を防ぐため定期的なレビューと運用改善が大切である。情報端末が果たす役割が拡大する社会においては、単なるシステム導入ではなく、人的・技術的両面から総合的な対策を練りあげることが必要不可欠な時代となっている。近年、コンピューターやスマートフォンなどの情報端末の普及により、業務効率の向上と同時にサイバー攻撃のリスクが急増している。従来のファイアウォールやネットワーク境界による防御策では、テレワークやクラウドサービスの浸透、多様な端末利用の拡大に十分対応できなくなっており、個々の端末を守るエンドポイントセキュリティの重要性が高まっている。エンドポイントセキュリティは、不正なプログラムやマルウェアの侵入検知と隔離、脆弱性を突く攻撃への対応、利用ログの監査やリモート制御といった多岐にわたる機能を持ち、内部不正防止にも寄与する。
特に、標的型メールや不正Webサイト経由の攻撃、利用者の誤操作によるウイルス拡散など、近年の多様化・巧妙化した攻撃に対しては、パターン検知に加え、ふるまい検知やサンドボックスなど複数の対策技術の組み合わせが不可欠である。また、管理面では組織全体のセキュリティポリシーと整合し、中央管理型での運用やアップデートの徹底が求められる。近年では多層防御の考え方が重視されており、クラウドサービスやネットワーク監視との連携によるリアルタイム対応が進化している。従業員の利便性とセキュリティのバランス、利用者自身の意識向上、そして継続的な運用改善が、今後一層不可欠になっていくだろう。